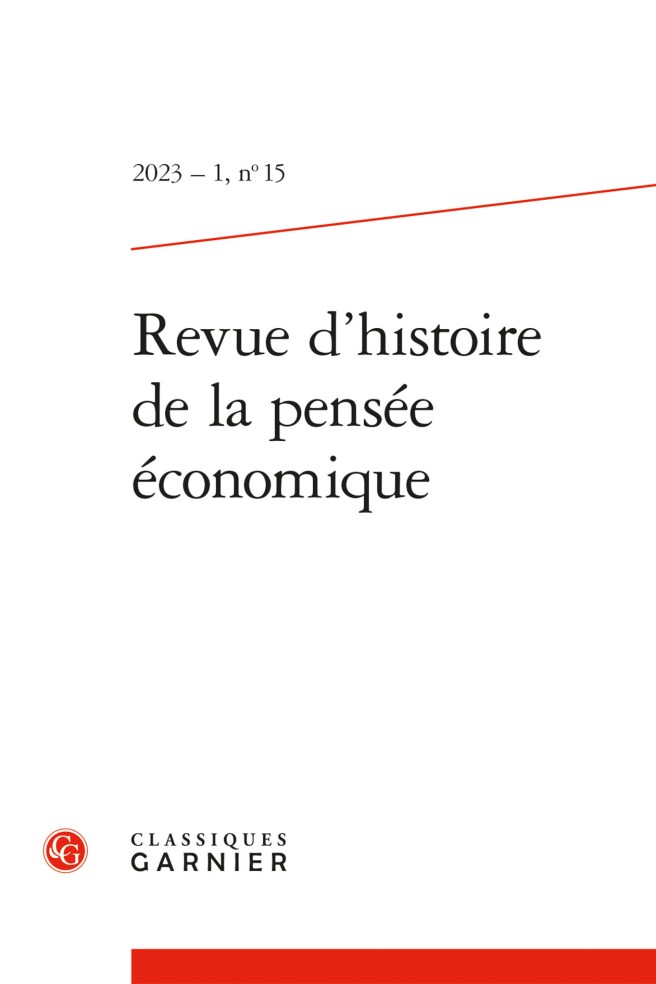I am an economist specializing in the history of economic thought and a professor at Shiga University in Japan. My research focuses on Walras’s economic thought, as well as the history of French economic thought and entrepreneurship.
経済学者(経済学史 • 経済思想)/ 滋賀大学経済学部教授
(研究分野)ワルラス・フランス経済学史・アントレプレナーシップ

My latest books


ワルラス『社会経済学研究』の初の日本語訳を2023年に刊行しました。Amazonはこちら
The first Japanese translation of Léon Walras's Études d'économie sociale (the second edition 1936), by Kayoko MISAKI and Hiroshi YAMASHITA was published in 2023.
My latest articles